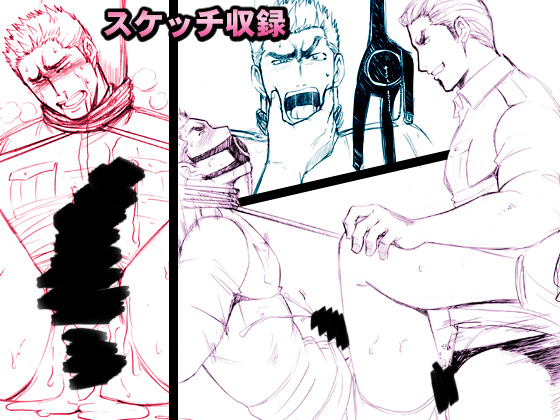「こんな片田舎に転属なんて、正直キミも嫌気がさしたろ?」
「嫌気だなんて、ここはとってもいい場所じゃないですか。海も綺麗で空気も良いし、それに何より行き交う人たちがみんな楽しそうで活気に溢れてて。僕は一目で気に入りましたよ」
「へえ、そうかい?都会から転属してきた男前にそう言ってもらえると、俺たち地元民も鼻が高いな。なあ、そうだろ?キース、アルバート」
穏やかに凪いだ海面を照らす日差しが、ゆっくりと傾き始めたオレンジ色の空の下、四人の男たちは狭い車内で柔らかな声を交わしていた。
「それにしても、すみません。こんな風に車に乗せてもらって……巡回の途中だったんじゃないですか?」
「いやいや、気にしないでくれ。ちょうど俺たちもパトロールが終わった所でね。ここはキミのいた都会と比べれば狭い町だ。定時の警備や巡回も、あっという間に終わってしまう。で、残った時間はさっきみたいにダイナーで食事をしたり海岸通りをぶらぶら歩いたり……まあ、良く言えば地域住民たちと親睦を深めてる。悪く言えば……はは、サボりの不良保安官さ」
ハンドルを握ったまま振り返らずに笑う男に、ウィリアムは笑顔で相槌を打ちながら、我知らず車窓の外に目をやった。
きらきらと爆ぜるサンセットが、背後の海に反射して、リアウィンドウから狭い車内へ降り注いでいる。
「……すごい、景色ですね」
思わず呟いたウィリアムに、隣に座ったアルバートが、いたずらっぽい笑みを浮かべて静かに告げる。
「ああ、ここの名物のロマンティックなサンセットだ。これを見せりゃあ、どんなにガードの固いカワイコちゃんでも、あっという間にノックアウトだ。どうだ?お前も思わず、俺に抱かれてもイイって思っちまったか?」
「え、ええ…?!」
未舗装の道を行く前輪が、緩いカーブをゆったり描くと、年季の入った車体からはギシギシと鈍い音色がこぼれ落ちる。
錆びついたサスペンションの声を聞きながら、ウィリアムはうっそうと茂る針葉樹の木々に阻まれて、徐々に明るさを失っていく窓外の景色にふと言い知れぬ不安感を駆り立てられた。
一体、どこまで行くんだろう――。
「……随分、細い道ですね」
ウィリアムが努めて平静に声を上げると、運転席からは変わらぬ朗らかな声色が言葉を返す。
「ああ、この道は山を抜けて向こうまで続いているんだけどね。見ての通り、未舗装で、細くて曲がりくねってるだろ?おまけに何年か前にこの道で観光客が暴行される事件が多発してね。おかげで今じゃ滅多と通る人はいない道になっちまった。地元じゃここを『スネークロード』なんて呼んでてね。ま、つまり俺たちは今、細い蛇の腹の中を通って目的の場所に行こうとしてるって訳だ」
「……」
「なに、心配しなくても大丈夫だよ。そんな事件はもう昔の事だし、それになにより、今キミが乗ってるこの車には、この町の正義を守る保安官が四人も乗っているんだ。万一にも、何か良からぬ事件を起こそうとしている輩が現れたら……その時は俺たちで返り討ちにしてやろうじゃないか。なあ、ウィリアム?」
朗らかに笑う運転席の男の声に、言葉の代わりに曖昧な笑みを放り返すと、ィリアムはかげり始めた車外の景色に目を移し、今一度ウィンドウに映る自分の顔をまじろぎもせずに凝視した。
この時、まだ彼は知らなかったのだ。
細く曲がりくねったこの山道の先で、自分を待っている物が何なのかを。
優しげな声を上げる新たな職場仲間の男たちが、本当はどういう視線で自分自身を見つめているのかを。
「…………」
行きつく先も、そこで待ち受ける凄惨な景色も、何も知らないまま、彼は、ウィリアムは――。
「目的地まではもう少しだから、あとちょっと、その狭いシートでガマンしてくれよ?」
運転席から投げかけられる陽気な声に鼓膜を打たれて、ウィリアムは短く笑って頷いた。
けれど、後になって彼は身をもって思い知る事になるのである。
あの時に、逃げていれば――。
だが、少なくとも、今の彼はまだ。
「さあ、それじゃあ今度は、ウィリアムが自分の事を話してくれよ――」
大きく開かれた大蛇の口以外に、自分を生きたまま丸呑みにしようとしている、鋭利な牙を持った捕食者が存在する事に……気付く事ができなかったのだ――。CLUB-Zによるカラー挿絵7枚(差分含め17枚)+モノクロスケッチ収録。