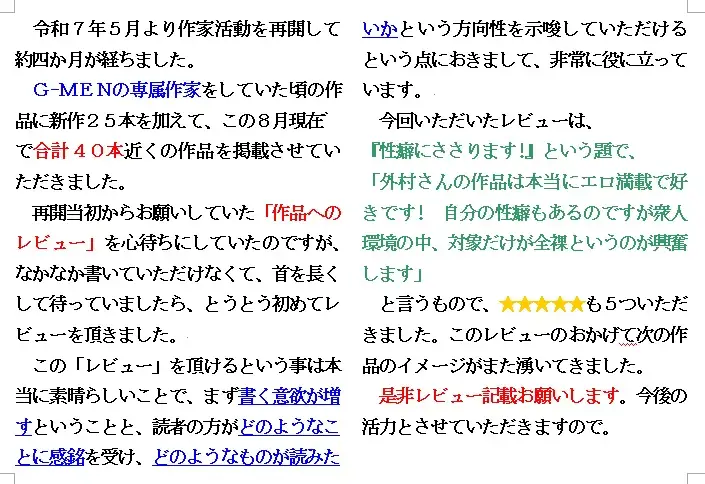忠誠心と男気 城山大学体育会レスリング部
二発目のビンタが終わると、伝統的に言う言葉は決まっていた。キャプテンが言った。
「気合を入れていただきありがとうございました。自分たちは甘かったと思います。下級生がきちっと仕事ができないのは最上級生である四年生がたるんでいたということです。申し訳ありませんでした。そのために自分たちはもっと反省が必要だと思います」
「そうだなぁ、よく言った。どんな反省が必要なんだ」
「はい、まず気合が足らなかったということです。レスリングの技術や身体的体力などと言う物理的な問題ではなく、心が甘えていたと思います」
「そうだな。心がちゃんとできていれば、様々な手落ちはなかったはずだ。心に入れるためにはどうしたらいいんだ」
「はい、それはやはり監督やコーチの方から気合をいただくしかないと思います」
「どんな気合だ?」
「はい、それは監督やコーチの男根をしゃぶらせていただいて、口の中に監督やコーチの熱い思いの入った精子を口に注いでいただき、私たちがそれを飲み込むことによって、気合を入れていただくということであります。
精子を飲むと言う事は、その方の大切な気合いの一部を分けていただけるということですから、それが体に注がれることによって伝統と言うのが受け継がれていくのだと思います」
「そうだな、では早速始めろ」
もう二つパイプ椅子が監督の右側左側に置かれ、そこにコーチが座ると、
「お前たちも脱げ」
と監督がコーチ二人に命じたので、城山の卒業生の桃岡はすぐ全裸になったが、今年城山に来た新人の杉下は戸惑っていた。
「何をもたもたしてるんだ。すぐ脱げ」
そう言われて、杉下は『ここは監督にさからってはいけない』と肌で感じてので、恐る恐る服を脱いで監督の横に座った。
監督も自ら服を脱いだ。
監督はもうすでに四十代後半であったが、毎日ずっと筋トレを続けていたので物凄い体をしていた。もちろんコーチ二人は言うまでもなく、現役を引退してからまだ少ししか経っていないので、二人とも凄い体をしていた。
若い部員達よりも肩も腕も尻も太腿もパンパンに筋肉が盛り上がっていた。
椅子の真ん中に大きな丸い穴が空いていた。つまりフェラチオすると同時にもう一人がケツの穴を舐められやすいように設計した椅子だった。
キャプテンの藤沢が言った。
「おい黒岩、一人足りないからお前も加われ」
三年生の黒岩も急いで全裸になると、四年生の中に加わって、二人ずつが組んで、監督、コーチのチ●コをしゃぶる係りとケツの穴を舐める係に分かれた、残りの下級生たちは皆それをじっと見ていた。
二年生、三年生は当然、成り行きを知っていたので動揺せず黙ってみていたが、一年生は今目の前で起こっていることに驚愕していた。
四年生は既に完全にギンギンに勃起した監督とコーチのチ●コを激しく咥え、頭を信じられないスピードで上下に動かして、ぺちゃペちゃといやらしい音を立てながらフェラチオを続けた。
ケツの穴を舐める舌の音もそれに加わって、監督やコーチのケツの穴がどんどん開いて柔らかくなっていくのを舐めてるやつは舌先で感じていた。
監督が言った。
「交代しろ」
そうするとフェラチオしている者とケツの穴を舐めている者がポジションを交代した。
「だめだ、だめだ。そんな心のこもってないフェラチオだったら、お前たちに気合いを注ぎ込んでやることはできない」
「すいませんでした。もっと心を入れてしゃぶります」
「ケツを舐めてるやつは、もっと奥まで舌を入れろ。舌をとがらせてケツの穴の中まで舌を入れるんだ。そしてケツの中で舌をぐるぐると動かせ」
一年生は茫然としていた。先輩たちが全裸にさせられたこともびっくりしたが、その後はビンタが行われ、そして今度はフェラチオとケツの穴を舐めると言う信じられない展開になっていったからだ。
ところがこれらの行為を見ていた二、三年生たちの股間も少しつ膨張し始め、ユニフォームの股間にテントを張り出していた。
さすが一年生のチ●コはそのような事はなかったが、二、三年生は最初からこういう展開になることがもうわかっていたので、自然とチ●コの容積が増していったのだ。それにしても杉下は、いきなり四年を全裸にさせたり、顔にビンタをしたり、その挙句の果てに、今度はフェラチオやケツの穴を舐めさせるといった展開そのものに驚いていたが、監督の命令には逆らえなかったので、じっと堪えていたが、心の中は嵐のように穏やかではなかった。
なんといっても一番怪訝に思った事は、それらのことを最上級生にしていると言う事だった。これは杉下がいた緑川大学では考えられないことだった。
しかし、杉下は部員たちが見ている前で、自分がチ●コをフェラチオされたり、ケツの穴を舐められることに妙な興奮を覚え始めていた。◆挿絵9枚入り
◆紹介画像、サンブルにAI生成画像を使用しております。