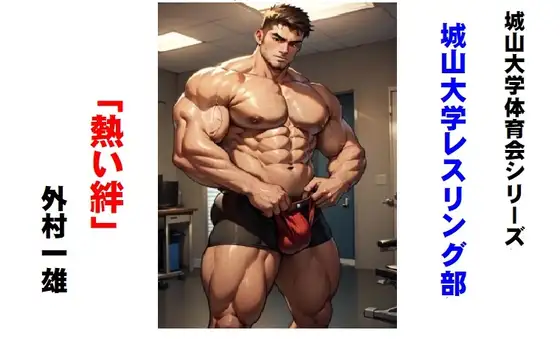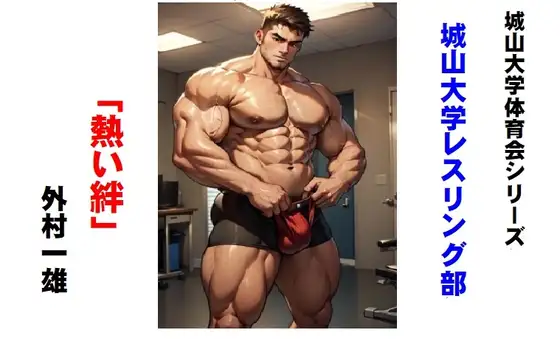
城山大学レスリング部「熱い絆」
「全員 整列! ボンボンはずせ!」と言われて下級生達はフラフラな状態ながらも、できるだけすばやく立ち上がって直立不動の姿勢をとった。みるとボンボンがついている者などほとんどいなかった。あれだけもがきあえばはずれて当たり前だった。
「よし!てめーら、今日の敗因は筋力がないのと技がないのと根性がないからだ!今から最後の根性をいれてやる」そうコーチが言った
「全員、男の根性みせたれ!」
二年の先輩は過去に体験済みだったせいか、すばやくチ●コに手をもっていくと激しくシゴキだした。
「自分の根性が足りませんでした!」と叫びながらやるのが伝統らしい。
「ホラ、早く一年もやれよ!」それぞれが、大声で
「自分のー!根性がー!足りませんでした!」と大声で叫びながら、つぎづきと激しく射精していった。すごい量の精子が飛び散った。
遠藤は毎日が苦しかった。部の先輩として、とるべき態度はわかっていたが、ついそれ以上の感情をもってしまう自分に当惑していた。だから今日の練習中も、いつもと違うボンボンをつけてのシゴキというシュチュエーションも加わって遠藤のチ●コははちきれるばかりにいきり勃ってしまった。
いつしか村田の硬いチ●コをくわえてみたいと思うようになり、その妄想はいつしか村田に犯されたい、つまりは村田の硬直した熱いチ●コで自分のケツをズボズボにしてほしいという願いへと変わっていった。
しかし現実には先輩と後輩。そんなことは夢のまた夢。裸族同然のレスリング部の生活で村田の裸が見られることだけでも有難いと思わなくてはいけないと自分を制していた。
遠藤は掃除中なのに自分のチ●コが勃起していることを知られないようにするのがたいへんだった。全裸だから隠すのが大変だった。
「村田、俺……、話あるんだけれど聞いてくれるかな」
「え?なんすか?そんなにあらたまって、いいっすよ、なんでも言ってください」
少しの沈黙が流れた
「実は、俺、おまえのこと好きなんだ」
「なんだあ、そんなことっすか、俺だって先輩のこと好きっすよ」
「いや、そんなんじゃなくて……つまり……その……男女の恋愛関係のような……そんな感情で、おまえのことが好きなんだ」
「え、それって、どういうことですか?俺マ●コついてないっすよ」
「いや、そんなことじゃなくて……」
「先輩、もしかしてオカマなんですか?そんなことないっすよね。だって全然女ぽくないどころか、むしろ熊みたいですからね」
「あのな、村田……熊でも熊が好きになることがあるんだよ」
「自分が熊っすか?いやいや俺はバンビですよ」って村田は冗談でも言って、この沈鬱な空気をなんとかしようとしていることが遠藤にはよくわかった。